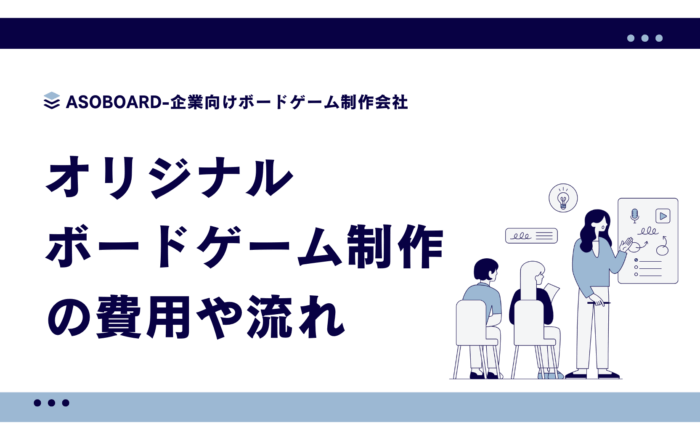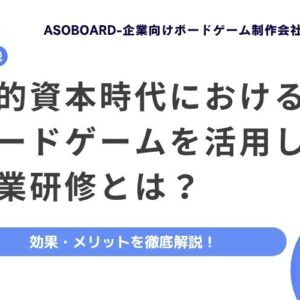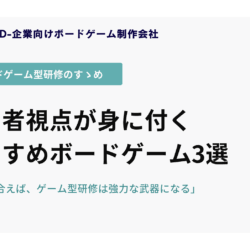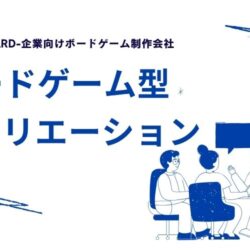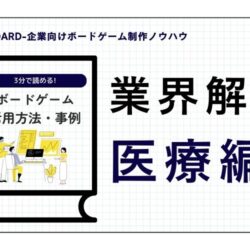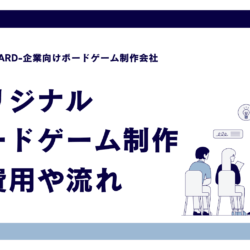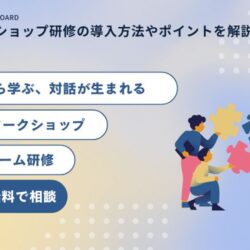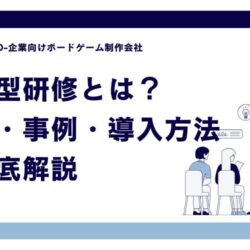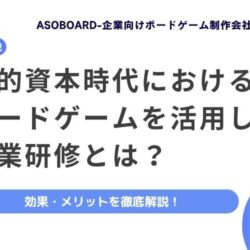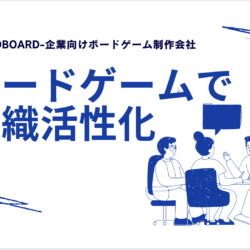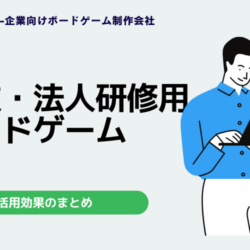「研修や採用イベントにオリジナルのボードゲームを取り入れたいけれど、どんな制作会社に依頼すれば良いのか分からない」
そんな悩みを抱えている担当者は少なくありません。実際、「ボードゲーム 制作会社」と検索しても、費用の目安や制作の流れ、依頼先の比較軸は分かりづらいのが現状です。
本記事では、ボードゲーム制作会社に依頼するメリットや制作フロー、費用感、実際の活用事例までを解説します。これからボードゲームの制作検討を始める方が“最初の判断軸”を持てるよう、網羅的にまとめました。
合同会社ASOBOARDでは、貴社の目的・課題に合わせた最適なオリジナルボードゲーム開発や研修プログラムの設計を専門としています。まずはお気軽にご相談ください。
<ASOBOARDの強み>
- ビジネス課題をゲームに落とし込める課題解決のプロ集団
- 事業開発、採用コンサル、マーケターなど、複合的な専門性を持つメンバーで提案
- 企画から製造までの一気通貫に加え、ルール検証やデザインのみなど柔軟なご支援が可能

品質責任者
メーカーでハード製品エンジニアとして培った、妥協なき品質へのこだわりを持つチーフクオリティオフィサー。最高の製品・サービスの実現に貢献します。
ボードゲーム制作会社が注目される背景
近年、企業研修や採用イベント、自治体の地域活性施策、学校教育の現場で「オリジナルボードゲームを制作したい」というニーズが高まっています。背景には、下記の3つの分野での変化があると考えます。それぞれについて解説していきます。
- 研修・教育の分野:一方的に知識を伝えるより、体験を通じて学ぶ「エデュテインメント」型の研修が重視されるようになった
- PR・マーケティングの分野:SNSで拡散される体験型コンテンツの需要が高まり、企業や観光地の魅力を「遊び」で伝える施策が増えた
- 地域社会の分野:地域の歴史や文化をボードゲームで学ぶイベントが注目され、観光や教育にも波及している
ボードゲーム制作会社の注目背景①体験型学習・研修の普及

従来の研修や教育は講義形式が主流でしたが、近年は「体験を通じた学び」が重視されています。
- 参加者自身が意思決定を行う
- 他者と協力・交渉を通じて学ぶ
- 成果を振り返ることで知識が定着する
このようなプロセスは「ゲーミフィケーション」と呼ばれ、教育・人材育成の分野で強く支持されています。既存の市販ボードゲームを応用するケースもありますが、自社特有の課題や育成テーマを反映するにはオリジナル設計が必要となり、制作会社への依頼が増えているのです。
ボードゲーム制作会社の注目背景②PR・マーケティングにおける「体験価値」の重視
SNSやWeb広告が溢れる中で、単なる情報発信では差別化が難しくなっています。そこで注目されているのが「体験を通じたブランド理解」です。オリジナルボードゲームには、
- イベント会場で遊んで盛り上がれる
- 家に持ち帰って繰り返し遊んでもらえる
- SNSで写真・動画が共有されやすい
といった特徴があり、ブランド認知や地域PRの強力なツールになっています。「遊びながらブランドを理解してもらえる」手段として、制作会社の活用ニーズが増加しています。
ボードゲーム制作会社の注目背景③多世代・多人数が参加できる
ボードゲームはデジタルスキルや体力に依存せず、子どもから高齢者まで同じルールで楽しめるため、多世代交流や地域イベントに最適です。
しかし、大人数イベントや特殊な利用条件に既存ゲームをそのまま適用するのは難しいケースも多いです。そこで、対象人数や会場条件に合わせたカスタマイズ設計を行えるボードゲーム制作会社が選ばれるようになっています。
ボードゲーム制作会社の注目背景④既存ゲーム活用の限界
市販の人気ゲーム(カタン・人狼・ドブルなど)は確かに完成度が高く、研修やイベントでも応用できます。ただし、以下のような限界があります。
- 自社の理念やメッセージを反映できない
- 毎回同じゲームでは飽きられる
- PRやブランド価値の訴求には直結しない
こうした課題を解決するために、目的に最適化されたオリジナルボードゲーム制作のニーズが高まっています。このように、オリジナルボードゲームは「遊び」と「学び」「伝える」を融合できる手段として活用されています。そして、その実現を支えているのが「ボードゲーム制作会社」です。
ボードゲーム制作会社選びで迷ったら、まずは「何のために作るのか」を一緒に考えてくれるパートナーを選びましょう。
ASOBOARDは単なるボードゲーム制作会社ではありません。貴社の経営課題や採用課題を深く理解し、成果にコミットするプロフェッショナル集団です。企画から製造まで、あるいは特定の一部工程だけでも、柔軟に対応いたします。
「ボードゲーム制作会社へ依頼」「既存のボードゲームを活用する」どちらが適切か

オリジナルボードゲームの制作を検討する前に、多くの企業や教育機関がまず考えるのが「既存のボードゲームをそのまま活用する」という選択肢です。実際、市販されている人気ゲームにはルールがシンプルで盛り上がるものも多く、導入コストも低いため手軽に使えます。
一方で、研修やPR、教育など目的が明確な場面では、既存のゲームだけでは物足りない場合も少なくありません。ここで制作会社に依頼する意義が生まれます。
既存のボードゲームを活用するメリットとデメリット
既存のボードゲームを活用する場合のメリットとデメリットを紹介いたします。既存のボードゲームを知りたい方はこちら。
既存のボードゲームを活用するメリット
- 費用が低い(数千円〜数万円程度で購入可能)
- すぐに入手できる、すぐに遊べる
- ルールが既に洗練されており、完成度が高い
- 教育・研修でも応用可能なタイトルが多い(例:人狼、ドブル、カタン)
既存のボードゲームを活用するデメリット
- 自社の理念や研修目的を直接反映できない
- 繰り返し使うと「またこれか」と飽きられる
- PRやブランディング施策には適さない(自社らしさが出ない)
- 大人数イベントや特殊な利用条件には対応しづらい
ボードゲーム制作会社に依頼するメリットとデメリット
ボードゲーム制作会社に依頼した場合のメリットとデメリットを紹介いたします。
ボードゲーム制作会社に依頼するメリット
- 自社の課題や目的を反映した完全オリジナル設計が可能
- ブランドカラーやロゴを使い、デザイン面でも差別化できる
- 教育・研修・PRの目的に沿った「学びの仕掛け」を組み込める
- 参加者の年齢や人数に合わせて設計できる
ボードゲーム制作会社に依頼するデメリット
- 制作費用がかかる(50万円〜300万円が一般的)
- 完成までに3〜6ヶ月程度の時間が必要
- 試作・調整に時間を割く必要がある
ボードゲーム制作を依頼するべきか?
結論から言えば、目的と予算によって選び分けることが重要ですが、ボードゲームを一度制作してしまえば会社の資産になります。また、制作したボードゲームのルールをベースに、デザインだけアップデートしたり、一部のルールの加除を運用費用少なく行えます。
- 「短期間で手軽に導入したい」「低予算でまず試したい」
→ 既存ゲームの活用が適しています。 - 「理念やメッセージを体験として伝えたい」「研修・PR・教育の効果を最大化したい」
→ 制作会社に依頼してオリジナルボードゲームを制作するのがおすすめです。
特に企業研修や採用イベント、自治体PRのようにその場限りではなく、記憶に残る体験が必要なケースでは、オリジナルボードゲーム制作の価値が際立ちます。
「インシデント削減」や「企業理念の浸透」など、会社固有の深い経営課題は、市販のゲームでは解決しきれません。
ASOBOARDなら、貴社のビジネスモデルや組織風土をゲームルールに落とし込み、現場の課題に直接アプローチするオリジナルゲームを開発できます。
ボードゲーム制作会社へ依頼する理由
オリジナルボードゲームを自分たちで作ることも不可能ではありません。実際に紙とペンで試作品を作り、身近な人と遊んでみれば「ゲームらしさ」を感じることはできるでしょう。しかし、実際に研修やイベントで「参加者全員が楽しめ、学びやメッセージがきちんと伝わるゲーム」を完成させるには、専門的な知識と経験が欠かせません。ここで、制作会社に依頼する大きな価値が生まれます。
ボードゲーム制作会社に依頼すべき理由①ルール設計とバランス調整の専門性
ボードゲームの肝は「ルール設計」にあります。シンプルで直感的に理解できる一方で、奥行きや盛り上がりもある。そのバランスを取るのは簡単ではありません。
ボードゲーム制作会社は数多くの企画・テストを手がけてきた経験から、“短時間で理解でき、最後まで熱中できるゲーム体験” を設計できます。
ボードゲーム制作会社に依頼すべき理由②デザインと世界観の一貫性
参加者のモチベーションを左右するのは、ゲームの世界観やデザインです。カードの見やすさ、色使い、ブランドカラーやロゴの活用など、細部までこだわることで「自社らしい体験」を作り出せます。ボードゲーム制作会社に依頼すれば、ゲームルールとビジュアルの整合性を担保できます。
ボードゲーム制作会社に依頼すべき理由③製造と品質の安心感
カードやボードの耐久性、手触り、パッケージの完成度は、参加者の体験価値に直結します。
印刷や加工、パッケージングには専門知識が必要であり、ミスがあれば納品物全体に影響します。ボードゲーム制作会社は信頼できる製造ネットワークを持っており、見栄え・品質・納期の面で安心です。
導入・運用サポートまで含まれる
完成したゲームを「どうやって現場で使うか」も大切です。ボードゲーム制作会社に依頼すれば、ルール説明資料、司会進行マニュアル、場合によっては導入動画まで揃い、初めての担当者でもスムーズに運営できます。単なる「モノ」としてのゲームではなく、「すぐに現場で成果を出せるパッケージ」として納品されるのは大きな利点です。
ボードゲーム制作を弊社に依頼するメリット
弊社にボードゲーム制作を依頼するメリットは、下記3点です。単に「ゲームを作る」のではなく、企業の課題を解決し、参加者に記憶に残る体験を提供するパートナーとして伴走できる点が、弊社の大きな強みです。
- ビジネス・人事・マーケティングの理解に基づいた的確な設計
- 成果につながる合理性とデザイン性の両立
- 誠実で透明性の高いコミュニケーション
一般的な制作会社が「ゲームの完成度」を担保するのに対し、弊社はビジネス文脈を深く理解した上でのゲーム設計を強みとしています。単なる“遊び”ではなく、経営課題の解決や人事施策の推進に直結するボードゲーム制作を実現します。
ボードゲーム制作を弊社に依頼するメリット①ビジネス理解に基づく設計
私たちは事業開発やマーケティングの現場経験が豊富であり、クライアント企業のビジネス構造や戦略を理解した上で要件を整理します。そのため「目的を外さない合理的な設計」が可能です。単なるエンタメではなく、成果に直結する体験設計を提供できます。
ボードゲーム制作を弊社に依頼するメリット②マーケティング施策との連動
マーケティング施策や戦略の意図を理解し、その延長線上でボードゲームを企画します。たとえば採用イベントや展示会、PR施策においても、「ブランド理解」や「顧客接点の強化」といった狙いをブレさせることなくゲーム化できます。
ボードゲーム制作を弊社に依頼するメリット③人事業界での深い知見
弊社メンバーは人事業界で10年近い経験を有しています。制度設計、採用代行、タレントマネジメントシステムの導入など、幅広い人事施策を手掛けてきました。そのため、研修や育成のニーズを熟知しており、人事施策や研修プログラムに自然に組み込めるゲーム設計が可能です。
ボードゲーム制作を弊社に依頼するメリット④合理性とデザイン性を兼ね備えた制作
要件定義からデザインまで一気通貫で対応できるため、無駄のない設計プロセスと、視覚的にも洗練された仕上がりを両立します。
ボードゲーム制作を弊社に依頼するメリット⑤誠実なコミュニケーション
私たちは「制作しない方が良い」と判断すれば、はっきりとお伝えします。無理に制作を進めることはせず、クライアントにとって最適な選択を第一に考えています。そのため、プロジェクトを進める過程でも違和感のない誠実なコミュニケーションを心がけています。
一般的な制作会社と弊社の違い
| 観点 | 一般的な制作会社 | 弊社 |
| ビジネス理解 | ゲーム制作に特化。 ビジネス背景や事業課題の理解は限定的。 | 事業開発やマーケティング経験が豊富で、 経営課題や施策の背景を踏まえて設計可能。 |
| マーケティングとの連動 | 「面白いゲーム」を作ることが中心。 マーケティング施策や戦略との一貫性は弱い。 | 戦略理解・施策理解が深く、 採用・PR・イベント施策と自然に連動できるゲーム設計が可能。 |
| 人事領域の知見 | 研修用ゲームを手掛けることはあるが、 人事施策全般の理解は浅い。 | 人事業界経験10年のメンバーが在籍。 制度設計・採用代行・タレントマネジメントにも知見があり、 研修・人事施策と親和性が高い。 |
| ゲーム設計力 | ルール・世界観の設計に強み。 | ゲーム設計に加え、合理的な要件定義とデザイン性を両立。 ビジネス文脈に沿った体験設計が得意。 |
| 品質と仕上がり | 見栄えの良いゲームを納品。 | 見栄えはもちろん、 実際に使われ成果が出るかを重視して設計・制作。 |
| コミュニケーション | 制作を前提にプロジェクトが進む。 | 「制作が不要」と判断すればはっきり伝える。 誠実で違和感のないコミュニケーションを徹底。 |
「自社で考えたルールのバランス調整だけしてほしい」
「デザインと製造だけプロに頼みたい」。
そんなご要望にもASOBOARDはお応えします。
全工程を依頼する【一気通貫】だけでなく、【検証特化】や【製造特化】といった柔軟なプランで、貴社の制作プロジェクトを成功させます。
ボードゲーム制作の流れ

オリジナルボードゲーム制作は、思いつきや一度の試作で完成するものではありません。研修やPRなどの目的に合った「参加者が楽しみながら学べる体験」に仕上げるためには、複数の工程を順に踏んでいきます。ここでは、制作会社に依頼した場合の一般的な流れを解説します。
まず、全体的な流れは下記の通りです。このプロセスをしっかり踏むことで、単なる娯楽ではなく「目的に直結する体験設計」が実現できるのです。
- ヒアリング
- 企画立案
- プロトタイプ制作とテストプレイ
- デザイン制作
- 印刷・製造
- 納品・導入支援
ボードゲーム制作の流れ①ヒアリングと要件定義

最初のステップはヒアリングです。貴社がどんな場面で、誰に向けて、どのような成果を期待しているのかを丁寧に整理します。
- 目的:研修/採用イベント/PR/教育など
- 対象:参加者の人数・年齢層・背景
- 条件:プレイ時間・会場環境・予算・納期
この段階で制作会社は「ゴール」を正確に把握し、ゲームの方向性を定めます。この要件定義が甘いと、完成後に「目的と合わない」という事態になりかねません。
弊社では添付画像のように制作で必要な独自のヒアリングシートを用いて、抜け漏れなくヒアリングさせていただきます。
ボードゲーム制作の流れ②企画立案とコンセプト設計

次に、ゲームのコンセプトとシステム案を複数提案します。たとえば、下記のように、「どういう体験を通じて目的を達成するか」を決定し、参加者の行動パターンを想定してルール設計を進めます。
- チームで協力して課題を解決する協力型ゲーム
- 限られたリソースを奪い合う競争型ゲーム
- 物語を追体験しながら学べるストーリー型ゲーム
ボードゲーム制作の流れ③プロトタイプ制作とテストプレイ

企画が固まると、試作品(プロトタイプ)が作られます。紙や簡易カードで構成された仮のゲームを実際に遊び、参加者の反応を観察しながら改善点を洗い出します。
- ルールが理解しやすいか
- プレイ時間が長すぎないか
- 盛り上がりの山場があるか
- 一部の人だけが発言しすぎていないか
こうしたポイントを確認し、必要に応じてルールを改良します。テストプレイと改善を繰り返すことが、完成度を左右する重要な工程です。
ボードゲーム制作の流れ④デザイン・ビジュアル制作

ルールとゲーム性が固まったら、カード・ボード・パッケージのデザインに進みます。
自社のロゴやブランドカラーを反映し、見やすさと世界観を両立させることで、参加者が没入できる仕上がりになります。この段階で、ゲームは「研修やPRの目的を体現するコンテンツ」へと形を整えていきます。
ボードゲーム制作の流れ⑤印刷・製造
デザインが完成すると、印刷・製造へ移行します。カードの厚みや加工方法、ボードの材質、パッケージの仕様など、使用シーンを考慮した品質設計が行われます。
たとえば研修で繰り返し利用する場合は耐久性重視、PR配布用なら軽量・コンパクト設計など、目的に応じて最適化を行います。
ボードゲーム制作の流れ⑥納品と導入サポート
最後に、完成品の納品と導入支援が行われます。ゲーム一式だけでなく、次のようなサポートがセットになるケースもあります。これにより、初めての担当者でもスムーズにゲームを進行できる環境が整います。
- ルール説明資料
- 司会者用マニュアル
- 利用シーンに応じた運営アドバイス
複雑な制作プロセスも、ASOBOARDなら安心です。企画段階での要件定義から、テストプレイによる徹底的な検証、そして納品後の活用支援まで一気通貫でサポートします。
もちろん、「デザイン・印刷のみ」といったスポットでのご依頼も大歓迎です。
ボードゲーム制作費用の相場
オリジナルボードゲーム制作にかかる費用は、目的・規模・仕様によって大きく変動します。 「数万円で済むのか」「数百万円かかるのか」と不安を持つ方も多いですが、実際の相場は50万円〜300万円程度が中心です。
ボードゲーム制作費用の相場①研修・社内利用の場合
「まず試してみたい」「数十人規模で使えれば良い」という場合に適しています。
- 目安:50万〜250万円程度
- 社内研修や小規模イベントで使うためのカードゲームやボードゲームが中心。
- デザインや印刷も小ロットで対応するため、比較的低コストで制作可能。
ボードゲーム制作費用の相場②PR・イベント利用の場合
「ブランドや地域の魅力を体験として伝えたい」場合に選ばれる規模です。
- 目安:150万〜300万円程度
- 展示会・採用イベント・自治体PRなど、多人数が参加するイベント向け。
- デザイン性や世界観の表現にこだわり、数百部を印刷するケースが多い。
- マニュアルや司会進行用の台本、説明動画なども制作されることが一般的。
ボードゲーム制作費用の相場③多言語展開・商品化利用の場合
「全国展開したい」「海外イベントでも配布したい」といったケースに該当します。
- 目安:300万円以上
- 市販品として販売することを前提に、数千部を製造したり、英語・中国語など多言語化する場合。
- プロモーションツールやWeb連動施策を含めて進めることも多く、マーケティング施策と一体で考える必要があります。
ボードゲームの制作費用が変動する要素
制作費は単なる「印刷代」ではなく、以下の要素で変動するため、これらをどう設計するかで、最終的な費用が決まります。
- 企画・設計の複雑さ:協力型/競争型/ストーリー型など
- デザイン・イラスト制作の工数:描き下ろしイラストか、既存素材活用か
- テストプレイ回数:調整をどこまで重ねるか
- 印刷ロット数:少部数なら単価が高く、大部数ならスケールメリットが出る
- 付随資料の有無:司会進行マニュアル・ルール説明動画など
ボードゲーム制作費用は決して高くはなく、制作によって「離職率低下」や「事故防止」が実現できれば、高いROI(投資対効果)を生み出します。
ASOBOARDは経営視点で費用対効果の高い設計をご提案します。予算に合わせた段階的なプランニングも可能ですので、まずはご相談ください。
ボードゲーム制作会社の選び方・ポイント
ボードゲーム制作会社を比較・検討する際は、単に「費用が安い」「納期が早い」といった条件だけで選んではいけません。最も重要なのは、依頼側の目的を正しく理解し、それをゲーム体験に落とし込んでくれるかどうかです。価格や納期はもちろん大事ですが、それ以上に担当者の姿勢やコミュニケーションの質が成果を左右します。制作会社を選ぶ際には、次の観点を意識するとよいでしょう。
ボードゲーム制作会社の選び方①実績
自社の目的に近い事例を持っているかを確認しましょう。教育研修向けの成功事例、採用イベントでの活用、PR施策での成果などの実績は制作会社の強みを映す鏡です。
目的に近い事例を多く持つ会社ほど、自社のニーズに合った提案を期待できます。
ボードゲーム制作会社の選び方②得意分野
制作会社ごとに「得意とする領域」が異なるので、何を強みとしているのかを単刀直入にヒアリングすることを推奨いたします。
- 企業研修や人材育成に強い会社
- PRイベントやマーケティング施策に強い会社
- 学校教育や自治体案件に特化している会社
ボードゲーム制作会社の選び方③テストプレイ
ボードゲームは企画段階で完成するものではなく、テストプレイを通じた改善の積み重ねで完成度が上がります。何度も試遊を行い、参加者の反応を観察しながらルールや難易度を調整する体制を持つ会社かどうかは、成果を分ける重要なポイントです。
ボードゲーム制作会社の選び方④製造ネットワーク
印刷・加工・パッケージの品質が担保できるかも重要です。研修で繰り返し使用するなら耐久性、PR配布ならコンパクトさ、商品化なら量産体制と流通品質。制作会社がどのような製造ネットワークを持っているかは、安心して任せられるかの判断基準になります。
ボードゲーム制作会社の選び方⑤運用サポート
完成品を納品して終わりではなく、実際に現場でスムーズに運用できるかどうかもポイントです。
- 司会台本
- ルール説明資料
- 導入時のレクチャーや動画マニュアル
こうしたサポートを提供してくれる会社なら、初めての担当者でも安心して導入できます。
ボードゲーム制作依頼時のチェックリスト
| 観点 | 確認すべき内容 | なぜ重要か |
| 実績 | 目的に近い事例(研修・PR・教育など)があるか | 自社の利用シーンに合った提案力を見極められる |
| 得意分野 | 教育研修/PRイベント/自治体案件など、強みがどこか | 自社の課題にフィットする制作が可能か判断できる |
| テストプレイ体制 | 改善を重ねる仕組みがあるか、試遊回数をどれくらい行うか | ゲームの完成度はテストと改善に比例するため |
| 製造ネットワーク | 印刷・加工・パッケージの品質や量産体制を持っているか | 耐久性や見栄え、納期の安定性に直結する |
| 運用サポート | 司会台本、ルール説明書、導入支援が含まれるか | 現場でスムーズに運用できるかどうかを左右する |
| ビジネス理解 | 事業内容や施策背景を理解できる担当者か | 「目的に合致した体験設計」ができるかの判断基準 |
| コミュニケーション | 制作が不要な場合は正直に伝えてくれるか | 長期的に信頼できるパートナーかを見極められる |
合同会社ASOBOARDでは、貴社の目的・課題に合わせた最適なオリジナルボードゲーム開発や研修プログラムの設計を専門としています。まずはお気軽にご相談ください。
ボードゲーム制作における弊社の強み
弊社が強みとしているのは、ビジネス理解と人事領域での豊富な経験です。
さらに、必要以上に制作を勧めることはせず、「制作が最適解でない」と判断すれば率直にお伝えする姿勢を大切にしています。そのため、クライアント様には安心感を持ってご相談いただけます。
ボードゲームの制作会社選びで大切なのは、単に「作る技術」があるかどうかではなく、目的を理解し、体験設計に落とし込めるかどうかです。
実績や得意分野、テストプレイ体制、製造ネットワーク、運用サポートをチェックするとともに、コミュニケーションの質を重視することで、信頼できるパートナーを見つけることができます。
採用支援やインターンシップでのゲーム活用は、ASOBOARDの最も得意とする領域の一つです。学生に貴社のリアルな魅力を伝え、入社後の定着に繋がるツールとして、人事・採用担当者様の強力な武器となるゲームを制作します。
ボードゲームの活用事例
オリジナルボードゲームは、単なる娯楽ではなく、資産性のあるコンテンツとして多様な場面で成果を生み出しています。特に企業活動においては、①マーケティングやPRのためのコンテンツとして、②人材育成・研修のための教育コンテンツとして、大きく二つの文脈で活用されることが一般的です。
近年の傾向としては、とりわけ研修用途の需要が増加しています。背景には「人的資本経営の重要性の高まり」や「労働人口減少による離職率改善・定着率向上」という課題があり、ボードゲームがその解決の一助となり得ることが注目されているのです。

ボードゲームの主な活用事例
- 企業研修
協力型の課題解決ゲームを通じて、チームワークや意思決定力を養成。普段は見えにくいメンバーのリーダーシップやコミュニケーション特性が浮き彫りになります。 - 採用イベント
自社の理念やカルチャーを体験的に理解できるゲームを導入し、応募者に強い共感を生む。従来の説明会では得られない「体感による理解」が可能です。 - 自治体イベント
地域の名所や文化をテーマにしたすごろく型ゲームで、参加者同士の交流や地域への愛着を醸成。地域活性や観光促進にもつながります。 - 学校教育
環境問題や金融リテラシーをテーマにしたシミュレーションゲームを活用。生徒が主体的に考え、探究心を高めるきっかけとなります。
一方で、マーケティングの場面でも効果を発揮します。自社キャラクターやIPを題材にしたボードゲームをノベルティとして制作し、キャンペーンの特典や抽選施策に組み込む活用事例が増えています。最近ではアニメやゲームキャラクターとのコラボレーションゲームも登場し、コンテンツ産業や認知施策と相性が非常に良い媒体として注目されています。
ボードゲーム活用の効果とメリット

企業向けのボードゲームで共通している効果は、「遊びを通じた会話や交渉を通じて、気づきが生まれる」ことです。
業務知識を直接習得するものではなく、心理戦・協力・交渉といったプロセスを経ることで、
- 自分自身の思考のクセに気づく
- 他者の強みや考え方の違いを理解する
- チームとしてどのように意思決定すればよいかを学ぶ
といった「気づき」を得られることが最大の価値です。注意すべきは、ボードゲームは“知識をインストールする道具”ではないという点です。
「業務知識をそのまま習得できるゲームを作りたい」という誤った期待を持つケースもありますが、実際には知識習得ではなく、会話・体験・気づきの場を提供することが真の目的になります。
弊社のクライアント様でも、この本質をご理解いただいたうえで、自社独自の課題解決や研修目的に合わせたゲームを制作し、人事施策やマーケティング戦略の一環として高い成果を実現されています。
さいごに
「ボードゲーム制作会社」に依頼することで、目的に合った“唯一無二の体験”を形にできます。費用は50〜300万円程度が中心ですが、その投資で得られるのは「強烈に記憶に残る体験」と「繰り返し使える学習資産」です。
また。ボードゲーム制作は、単なるモノづくりではありません。企業のメッセージを「体験」として届け、組織や人の「行動」を変えるための戦略的な投資です。だからこそ、依頼先選びにおいては「ビジネス課題への理解度」と「サービスの柔軟性」が重要になります。
【無料】オリジナルボードゲーム制作・導入相談
弊社ASOBOARDは、お客様のニーズに合わせたサービス提供の柔軟性にあります。企画から全て任せたい企業様はもちろん、デザインなしでゲームルールの検証・バランス調整のみに重きを置きたい、あるいは企画・デザインは完了し印刷・製造のみを依頼したいといった、あらゆる制作段階に対応可能です。
- 企画から製造まで全て任せたい方は【一気通貫サービス】
- ルールのバランス調整のみ頼みたい方は【検証特化サービス】
- デザインと製造のみを依頼したい方は【製造特化サービス】
貴社のフェーズやリソースに合わせて、最適な形でプロジェクトを支援いたします。まずは「どんな課題を解決したいか」、その想いをお聞かせください。

品質責任者
メーカーでハード製品エンジニアとして培った、妥協なき品質へのこだわりを持つチーフクオリティオフィサー。最高の製品・サービスの実現に貢献します。